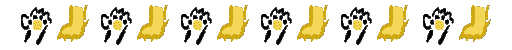
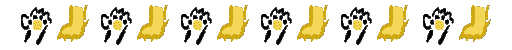
| 幸せの黒い猫 (作:L・J) ブレザーをだらしなく着た茶髪の少年、木下 祐也(きのしたゆうや)はイライラしながら帰路に付いていた。 今日高校で、同じサッカー部のチームメイトで親友の田中 駿(たなかしゅん)が何も言わずクラブを辞めていたからなのだ。 祐也と駿は学校中で知らない者が少ない位の仲の良い親友同士だった。 クラブでも祐也と駿、2人が揃うとどんな強豪との試合でも負ける気がしないと評判だった。 そんな時にいきなり駿がクラブを辞めてしまったのである、祐也は苛立ちを押さえきれなかった。 そこで偶然目に入ったのが道に落ちていた缶コーヒーの空き缶。 2009/01/03 22:29 祐也は辺りに人がいないのを確認してからその空き缶を思い切り蹴りとばした。 その空き缶は離れた場所にあった草むらに落ち。その時、 「ニャッ!」 と声がして黒い何かが飛び出してきた。 「え?」 その黒い何かはすらりとした1匹の黒猫であった。 「あ・・・・・・猫・・・・・・悪ぃ」 祐也は思わずその黒猫を見つめながら謝った。 そして祐也は足を猫のいる方向に進める。 その内猫も逃げていくと思ったのだ。 ところがその黒猫は祐也の顔をジッと見つめる。 そして祐也が黒猫の側を通り過ぎようとした時、突然 「わっ!」 猫が祐也の背中に飛び乗って来た。 「おま・・・・・・降りろよ」 祐也は当然の事ながら猫を降ろそうとする。 だが猫は 「フシャー!」 と祐也のブレザーにしがみつきながら威嚇してくる。 その上無理矢理降ろそうとすると爪を立てる。 「痛てててて、爪立てるなよ!」 結局祐也は背中に猫を張り付けながら帰るしかなかったのである。 「ただいま〜」 「お帰り、今日も遅かったわね。クラブも良いけどもっと早く帰れないの?」 そう祐也に話しかけたのは彼の姉、真美(まみ)である。 今彼らの両親はいない。父親は長期海外出張中、母親は大恋愛の末結婚した父親と1日でも離れたくないと言って付いて行ってしまったのである。 「それは良いけどさ、これ降ろしてくれない?」 「それは良いけどってなによ、あんた私の話聞いてんの?」 そう言った姉に向かって祐也は背中を向けた。 そしてそんな祐也の背中を見た真美は嬉しそうな悲鳴をあげた。 「キャア、なにその猫、可愛い」 「それがさ、道を歩いていたらこいつが急に背中に飛び乗ってきてさぁ」 「待ってて今取ってあげるから」 真美はそっと猫の爪を外していく。 「どうしたのお前、野良だったの?それとも捨てられたの?」 真美はまさに猫なで声で猫に話しかける。 すると猫は自分に話しかけてくる真美の顔をジッと見た後彼女の顔をしきりに舐める。 「キャッ、くすぐったい」 そう言いながらも真美はニコニコ顔だ。 そして突然 「この子飼う」 と言い出した。 「おい飼うって、父さん達に聞かずにそんな事決めて良いのかよ」 呆れ顔の祐也に真美は言った。 「後でメール送っておくわよ、それに2人共飼って良いって言うと思う。あんたは覚えてないと思うけど昔家には猫がいてたのよ。その時使ってた猫のトイレとか食器とか物置にまだあると思うわ」 「ふ〜ん」 祐也は姉との会話を終了して、家にあがる為靴を脱ごうとした。 「待って、今からこの子の餌買ってきて」 「え〜、今から?俺クラブの帰りで腹減ってるんだけど」 その言葉に真美は眉をつり上げた。 「なぁにその言葉は。ほんのちょっと近くにコンビニに行ってくるだけじゃないの。あんた失恋したばかりなのに家事を一手に引き受けている傷心の姉を助けてやろうとか思わないの?」 己の失言を悟った祐也は渋々と姉の頼みを引き受ける事にした。 「分かりました、行ってきます」 その途端、真美の態度がコロリと変わる。 「分かれば良いのよ分かれば。とりあえずカリカリを1袋買ってきて。あ、ご褒美にアイスでも買って良いわよ」 そう言って猫を床に降ろしながら真美は千円札を2枚、祐也に手渡す。 「行ってきます」 お金を受け取った祐也はドアのノブに手を かける、すると 「ニャ〜〜〜」 猫が祐也の足にじゃれ付いてきた。 これには祐也も驚いて困惑の表情を浮かべる。 「なんだよお前、外に行きたいのか?」 そんな祐也の言葉が分かったかのように猫はもう1度 「ニャ〜〜〜」 と鳴いた。 「ダメよ猫ちゃん、お姉ちゃんと一緒にお兄ちゃんを待ってようね」 真美が再び猫を抱き上げたが 「ニャニャニャッ」 猫は激しく抵抗する。 ついには真美の腕からスルリと抜けだし祐也の足下にやってきた。 その様子に真美は 「祐也、その子あんたと一緒にいたいみたいだから連れていったげなさいよ。私はその間に夕飯の支度しながらその子の名前考えておくから」 そこまで言われては祐也も観念するしかなかった。 そして祐也は猫をヒョイと抱き上げながらドアを開ける。 「行ってきます」 祐也はそう言って外へと足を踏み出した。 「オッ、そうだ最近できた新しいコンビニに行ってみよう」 猫を抱きながら足を進めていた祐也はそう独り言を呟いた。そんな祐也の腕の中で猫はゴロゴロと喉を鳴らす。 暫く歩いて目的のコンビニに着いた祐也だが、はたと気づく。店の中にまで猫は連れて行けない事を。 考えたあげく祐也は店外の目立たない所に猫を降ろした。 そして 「良いか、ここを絶対動くなよ」 そう言い含めて祐也は店に入る。 「え〜とカリカリはこれか・・・・・・。後はコーラでも買おうかな」 目当ての商品を全て手にし、祐也はレジに向かう。 真美から渡されたお札を広げながらレジ前に立った祐也は突然 「あっ!」 と言われて顔をあげた。そして驚く。 「駿!」 カウンター内でレジを打っていたのは親友の駿であった。 しばらく呆然としていた駿だがハッと我に返り、かけていた黒縁めがねをあげると慌てて祐也の差し出した商品の会計を始めた。 「975円になります、ありがとうございました」 そう言われて品物を差し出された祐也は駿に話しかけようとしたが出来なかった。 その前に駿が 「次のお客様どうぞ」 と、次の客の会計を促したからだ。 結局祐也は駿と何も話せないままコンビニを後にするしかなかったのである。 後ろ髪引かれる思いでコンビニを後にした祐也であるが、それと同時に猫を待たせていた事を思い出した。 「やっべ、あいつどっか行ったかも」 『ここで待ってろ』 とは言ったものの猫が犬の様に人間の言う事を聞くとは思っていなかった祐也だが、足早に猫を置いて来た場所に向かう。 はたして猫は言われた通りの場所にいた。 ただ猫の周りを2〜3人の中学生らしき女学生が取り囲んでいたが。 「や〜ん、可愛い」 「フワフワ〜♪」 「ここで何か餌でも買ってこようか」 女学生達はそんな事を言いながら猫をグリグリと撫で回す。 そんな風に何をされても身動きひとつしなかった猫だが、祐也の姿を見つけた途端、喜びいさんで祐也の元に走り出し、そして足下にすり寄った。 その様にびっくりした女学生達は今度は祐也に話しかける。 「その猫お兄さんの猫なんですか?」 「猫ちゃんの名前は?」 「お兄さんは高校生ですか?」 続けざまの質問に面くらいながらも祐也は答える。 「この猫は俺ん家で飼うことになった猫、拾ったばかりだからまだ名前は無い。そしてたしかに俺は高校生だけど」 そのまま祐也は猫を片腕に抱きかかえてその場を後にした。 そんな祐也と猫を見送った女学生達が 「超イケメン!」 「猫を抱いて歩く姿が可愛いよね〜」 「明日さやか達に自慢しようよ」 と騒いでいたが祐也は気づかなかった。 「ただいま〜」 抱えていた猫と荷物を真美に渡した祐也は買って来たコーラと玄関に置きっぱなしだった荷物がぎっしり詰まったスポーツバッグを持って2階の自室へとあがった。 散らかし放題散らかした部屋のほんの少し空いているスペースにスポーツバッグを置き、ペットボトルのコーラの蓋を開けようとした時、バッグの中から携帯電話の着信音が 聞こえてきた。 慌ててバッグを開け、携帯電話を取り出し通話ボタンを押した。 「はい?」 『祐也?』 「駿!お前何なんだよ!いきなりクラブを辞めるわ、バイトをするわ!ちゃんと説明しろよ!」 『説明するからちょっと出てこれないか?』 「今からか?」 『ああ』 「今から飯なんだよな〜」 『あ、そうだよな。じゃあ明日学校で説明する』 そう言って通話を終えようする駿を祐也は慌てて止める。 「待てよ駿!お前の方は飯は?」 『まだだけど?』 「じゃあ久しぶりに一緒家でに飯食おうぜ」 『でも迷惑じゃ?』 「んなわけないだろ、姉ちゃん駿を飯に呼んでもいいよな?」 祐也は階下にいる真美に向かって訪ねた。 「駿君?いいよ、久しぶりね」 ドアを開け、階下をのぞき込んだ途端カレーの臭いが漂って来た。 「良いってさ、それに今日はお前の好きなカレーだぜ」 『じゃあ今から行くから待っててくれ』 そう言った駿が電話を切ってから10分程して玄関のチャイムが鳴った。 「よく来たなあがれよ」 「お邪魔します」 祐也に促され居間に通された駿は、大きなちゃぶ台に配膳をしていた真美に声をかけた。 「真美さん今晩は、お久しぶりです」 「いらっしゃい駿君、久しぶりねえ。あ、今サラダ持ってくるから座ってて」 「はい」 駿は今まで何度もこの家に来て食事をごちそうになっていた。だから座る為の定位置も決まっていたので自然とその場所に置いてある座布団に腰をおろした。 その時 「ニャ〜」 黒猫がやってきて駿のあぐらをかいた足に身体をすり寄せた。 「わっ、猫!」 「ああ、今日いきなり俺の背中に飛び乗ってきたんだ」 「ああ、だからキャットフードを買ってたのか」 「姉ちゃんこいつの名前もう決まった?」 駿の向かい側に腰をおろした祐也が真美に聞く。 「決めたわよ。この子の名前はロック」 「ロック?変な名前」 「いいでしょ、どんな名前付けても。とりあえず明日ロックの首輪買ってくる」 「いいけどさ、さあ食おうぜ」 3人はスプーンを手に取り食べだした。 するとロックが 「ニャー」 と祐也の皿のカレーの匂いをかいで舐めようとした。 それに気付いた祐也は慌ててそれを止める。 「あ、こら人間の食い物を食べるな」 すると今度は真美が言う。 「あ、まだロックに餌やってなかった、おいでロック」 そう言って台所に立つ真美の後についてロックも台所に向かう。 真美が台所に行ったのを確認して祐也は駿 に尋ねた。 「で、なんでクラブを辞めてバイトを始めたんだ?」 一心不乱にスプーンを動かして口に運んでいた駿はとりあえず皿を空にしたことで落ち着いたのかため息をひとつ付いた。 そして祐也に 「お代わり良いか?」 と尋ねた。 その言葉に祐也はプッと吹き出した。 「待ってろ」 駿の皿を受け取った祐也も台所に行き、それと入れ違いに真美が戻って来て、そしてすぐに祐也も戻って来た。 「ほらよ」 駿の前に2杯目のカレーが入った皿を置いて祐也は定位置に座る。 「で、さっきの話だけど今言えるのか?姉ちゃんには聞かれたくないなら後で部屋で聞くけど?」 駿はスプーンをご飯に突っ込みながら答えた。 「ううん良いよ、別に隠す様なことじゃないから。実はさ、俺の親父がリストラにあったんだ」 「リストラ?大丈夫なのか?」 真美も祐也もスプーンを動かす手を止めた。 「うん、兄貴もお袋も働いているから生活費はギリギリ何とかなってるんだけど、学費や小遣いまでは出せないからバイトで稼いでくれって言われたんだ」 「そうだったのか、で、おじさんは?」 「毎日の様にハローワークに通ってるんだけど年も年だしこの不景気だしでなかなか仕事が見つからないってこぼしてるよ」 「そうか、何かいい仕事が見つかれば良いな」 「うん」 そんな会話をしていた3人はロックが台所からその会話をジッと聞いている事には気付かなかった。 翌朝、洗顔を済ませた祐也が朝食を食べようとちゃぶ台の定位置に座るとなぜかいつもは1つしかない弁当の包みが2つ置いてあった。 「おはよう祐也」 真美は湯気が立つ味噌汁が入ったお椀を祐也の前に置いた。 「ああ、おはよう。それより姉ちゃん何で弁当が2つあるの?」 「1つは駿君の分よ。昨日お昼は水を飲んで我慢してるって言ってたじゃない。私達では駿君のお父さんに仕事を紹介してあげる事なんて出来ないけど、お弁当を作ってあげる位なら出来るものね」 真美のその言葉に祐也は照れながら感謝の言葉を口にする。 「ありがと。駿も喜ぶよ」 その後朝食が終わり弁当の包み2つをスポーツバッグに詰めていた祐也の所に餌を食べ終わったロックがやって来て身体をスリッとすり寄せて来た。 そのままフンフンと祐也の匂いを嗅ぎ、背中に登って来る。 「いって〜〜〜!」 祐也は思わず悲鳴を上げる。 そんな祐也の悲鳴を聞きつけて真美が飛んできた。 「どうしたの祐也、やだちょっと可愛い」 「可愛いじゃねえよ、こいつ何とかしてくれよ」 ロックは祐也の背中に登った後、肩まで移動し、そのまま右肩に爪をたててしっかりと掴まっていたのだ。もちろん足指の爪もたてている。 「早く取ってくれよ」 困り果てた祐也が真美に懇願したが彼女は笑いながら携帯電話を取り出す。 「あはははは、ちょっと待って、写真撮るから」 そう言いながら真美は痛みをこらえながらも憮然とした顔をしている祐也ごとロックの写真を数枚撮った。 ひとしきり写真を撮るとようやく祐也の背中からロックを降ろした。 「ロックはお兄ちゃんが大好きなのねえ」 真美はロックの顔をのぞき込みながらそう言う。 すると祐也は 「おいおい、好きなのは構わないけど背中に登るなよ、痛てぇんだからな。じゃ、行ってきます」 そう文句を言って出て行った。 そんな弟の様子を真美は笑いながら先程撮ったロックの写真付きで友人にメールするのであった。 その日の昼休み、祐也は図書室でサッカー関係の雑誌を読んでいた駿を連れ出した。 「これ弁当。姉ちゃんがお前にって」 そう言われて渡された包みに駿はパァッと顔を輝かせた。 「マジ?ありがとう」 2人はあまり人が来ない裏庭に設置してあるベンチに腰掛けて弁当を食べ始めた。 「ところでさ、コンビニのバイトは何曜日にしてるんだ?」 動かしていた箸を止めて駿が答える。 「なるべくたくさん稼ぎたいから土日と火水」 「他の場所には?」 「いや、今の所コンビニだけ」 「え、じゃあサッカー部が水木金だから、木金だったら部に顔出せるんじゃねえの?」 「いや、ついこの間辞めたばかりなのにすぐに復帰するのっておかしいだろ」 「そうかなあ、俺は気にしないけど」 「他の奴が気にするって。がんばって国立に行ってくれよ。その時は絶対応援に行くから」 「国立って・・・・・・、お前すげえプレッシャーかけるなぁ」 「いいじゃねぇか、お前はプレッシャーがかかればかかる程力を発揮するタイプなんだからさ」 祐也と駿がそんな会話をした日の放課後、真美がいつになく上機嫌で帰って来た。 「姉ちゃんえらく上機嫌だなぁ」 ロックの餌皿にキャットフードを入れながら祐也がそう聞くと真美は満面の笑顔を彼とロックに向けた。 「それがね〜、今朝あんたの肩にとまったロックの写真を撮ったじゃない」 「うん」 「それを友達にメールで送ったのよ。でも間違えて他の人に送っちゃったのね」 「?それでなんで上機嫌になるんだ?」 「まあ話は最後まで聞きなさい。でね、その間違えてメールを送った相手が年下だけど課内一のイケメンエリートだったのよ」 「まさかそいつと仲良くなったとか?」 「そのまさかよ!私も知らなかったんだけどね、その彼、斉藤(さいとう)君って言うんだけど、斉藤君は猫が大好きなんだって」 「へえ」 「でね、この子は斉藤君の飼ってる猫。この子今妊娠中なんだって」 真美はウキウキしながら写メールを祐也に見せる。そこには腹が出ているが美形のキジ猫が1匹写っていた。 「この猫何て種類?」 「アメリカンショートヘアていうの、もうすぐ子猫が生まれるんだって」 「まさかその子猫を引き取るとか言うんじゃないよな」 「言わないわよ。この子こんなに綺麗だから子猫ももう貰い手が決まってるんだって」 「それならいいけどさ、それより弁当ありがとな。駿も喜んでいたよ」 「あら、それは良かった。駿君のお父さんのお仕事が決まるまで位は作ってあげるって伝えておいて」 「ああ分かった、明日会ったら伝えておくよ」 その言葉通り真美は自分の分も含めて3つの弁当を作るのが日課になった。 だが真美の日課はそれだけでは無かった。毎朝祐也の背中に登るロックを降ろすのも日課になったのだ。 毎朝制服のブレザーを着た途端に背中によじ登られ、その度に悲鳴をあげる祐也。そしてその祐也の背中からロックを降ろす真美。 この一連の動作が木下家の新たな習慣になりつつあったある日の事、珍しく祐也の背中に登らなかったロックが朝からそわそわしながら彼をずっと見上げていて、その後するりとどこかに歩いていった。 「なあ今日こいつ変じゃね?」 「そうねえ、今日はあんたの背中に登らないし」 「別に登らなくっても良いよ、痛てぇんだからな、爪を立てられるの」 そんな事を話していると突然 「ニャ〜〜〜〜〜〜!」 とロックが珍しく鳴き出した。 「あらどうしたのロック」 真美と祐也の2人が声のする方を見るとロックは玄関扉をカリカリと引っかきながら2人を見つめていた。 「なあにロック、外に出たいの?」 真美のそんな言葉にロックが 「ニャッ!」 と返事の様な声を出す。 「じゃあ待ってて、今出してあげるから」 そう言って玄関扉に向かう真美に祐也が 「そいつ今まで外に出た事ないんだろ?外に出して迷子になって帰って来なかったらどうすんだ?」 「大丈夫よ、迷子になっても首輪に私の携帯電話の番号書いてあるから」 ロックは今赤色をした皮の首輪をつけていて、その首輪にマジックで真美の携帯電話の電話番号が書いてあるのだ。 真美が鍵を外したドアを開けるとロックは外に出て、あっと言う間にどこかに走り去って行った。 そんなロックを見ながら真美は呟く。 「今度ロック用の猫入り口作ってもらおうかしら」 すると祐也が呆れながら言う。 「ロックが外に出て行ったのは今日が初めてなんだぜ。そこまでしなくてもいいんじゃね?」 「そうねぇ・・・・・・」 「おっと、もうこんな時間。じゃあ俺行ってくるから」 いつも使っているスポーツバッグを肩に掛け、祐也は学校に向かって歩き出した。 その日の放課後、サッカー部の練習の後クタクタになった祐也はボンヤリとしながら帰路についていた。 駿が抜けた穴を埋めるべく、様々な部員とペアを組んで相性の良い組み合わせを全員で探っているのだ。 そのままフラフラと横断歩道に足を進める祐也の背中に何か黒い物が取り付いた。 「いって〜〜〜〜〜!!!!」 祐也は思わず足を止める。 その時! 「ガッシャ〜〜〜〜〜ン!!!!」 祐也の目の前を信号無視の上、スピードを出しすぎたワゴン車が走り去り、そして電柱に激突した。 呆然とその光景を見ていた祐也に、彼の後ろから横断歩道を渡ろうとしていた中年女性が声をかけた。 「あなた大丈夫?」 「は、はい」 祐也は何とか立ち直り返事をした。 そんな祐也に女性は話し続ける。 「危なかったわね、あなたあのまま渡っていたらあの車にはねられていたわよ」 女性は電柱に激突し、助手席がベコベコにへこんだ車を指さし言った。 車の運転手は事故に気付いて救助の為に寄って来た人達に車外に出され、頭から血を流しながら歩道に寝かされていた。 「あなたの背中にひっついているその猫ちゃんが助けてくれたのね」 「猫?」 「ええ。待ってて取ってあげるから」 祐也の背中から猫を取り、祐也の方に顔を向けた。 「ロック!」 祐也の背中に取り付いていた猫はロックだったのだ。 「あら、この猫ちゃん知ってるの?」 「はあ、いやはい。うちの飼い猫です」 「まあちょうど良かったじゃない、はいこの猫ちゃん返すわね」 そう言われて受け取ったロックはゴロゴロとのどを鳴らしながら祐也の胸に顔をこすりつけてきた。 その時周りが呼んだ警察官が祐也の元にやってきた。 「君、あの車にはねられてたかもしれなかったそうだが何故無事だったのか、教えてくれないかい?」 「ああ、それは・・・・・・」 祐也が答え様とした時、先程の女性が警察官に説明する。 「実はね、この猫ちゃんがこの子を助けてくれたのよ」 「は?この猫がですか?」 警察官は不思議そうな顔をしながらロックをマジマジと見つめる。 「この猫は俺んちの飼い猫なんですが横断歩道を渡ろうとした時に背中に駆け登ってきたんです。で、思わず足を止めたら車が通り過ぎて行ったんです」 「ほう」 警察官は何やら書類に書き込みをしながらもう1度ロックを見る。 「黒猫は不吉だとか言う人もいますが、君にとってこの猫は命を助けてくれたラッキーキャットなんだね」 結局警察に住所・氏名・電話番号を聞かれた後早々に解放された祐也が荷物とロックを抱えて帰宅すると真美が慌てて玄関にやって来た。 「祐也、あんた車にひかれかけたって?」 真美のその勢いに祐也はたじたじとなる。 「なんで知ってんだ?」 「さっき警察から電話があったのよ」 「なんだ、しかし警察も別にケガもしてないんだから言わなくてもいいのにな」 祐也は靴を脱ぎながらロックを廊下におろした。 そのままスポーツバッグを抱えながら居間に向かった祐也はちゃぶ台に乗っていたバナナを口にする。 そんな祐也に真美が怒りながら言う。 「そんな言い方ないでしょ。私はあんたの面倒をみる義務があるんだからちゃんと説明しなさい」 「分かったよ、分かったからとにかく何か食べさせてくれよ腹減ってしょうがないんだから」 祐也は二本目のバナナの皮を剥きながら懇願した。 「もう!」 その時、プンプンと腹を立てている真美の足下にスリッと身体をこすり付けたロックが「ニャー!」 と甲高い声で鳴いた。 その途端真美の怒りのボルテージは急速にダウンした。 「なあにロックお腹空いたの?」 そう言いながらロックを抱き上げるとそれに答えるかのように 「ニャー」 ともう1度大きな声で鳴いた。 「はいはい今あげるね」 真美は台所に向かうと餌皿にカリカリのキャットフードを入れて、ロック用の所定位置に置いた。 「ニャッ♪」 嬉しそうな声をあげたロックは早速カリカリを食べ始めた。 そんなロックの様子を確認すると真美は祐也の前に座って説明を求めた。 「さ、ちゃんと説明しなさい」 「食い物は〜?」 「もうすぐ夕飯だから我慢しなさい」 「チェッ」 仕方なく祐也は冷蔵庫からオレンジジュースを取り出し缶に口を付けた。 それを一気に半分程飲み干し、口を開いた。 「横断歩道の信号が青になったからさ、渡ろうとしたんだよ。そしたらそいつが」 祐也は餌を食べ終わった後真美の膝にのって来たロックに視線をうつす。 「俺の背中に登って来てさ」 「あら!ロック、お外でもお兄ちゃんの背中に登ったの?」 「んで、痛くって思わず立ち止まったらそこを車が通り過ぎて行ったんだ」 その話を聞いて真美は目を丸くする。 「え?じゃあロックが助けてくれたの?」 「まあ、そうなるのかな?」 真美は思わずロックを抱き上げた。 「えら〜いロック!お兄ちゃんを助けてくれたのね!」 テンション高くロックを抱っこしている真美に祐也は言う。 「ちゃんと説明したから、早く飯にしてくれよ」 そう言われてハッと我に返った真美はロックを祐也に渡した。 「ごめんごめん、今用意するわね」 そのままコンロにフライパンを置いて火を着けた真美はニッコリと笑いながら言う。 「ロックが来てから良い事が良く起こるわね。黒猫は不吉だって言って嫌う人がいるけどロックは幸運のラッキーキャットね」 道でロックに助けられてからしばらくたった頃。勉強をしようと筆箱を開いた祐也は 「あ」 と呟いた。 そして階下に行き、真美に声をかける。 「ちょっとコンビニ行ってくるから」 その言葉に真美は 「あらそう、じゃあついでにロックのカリカリ買って来て」 と言い、祐也に紙幣を握らせる。 そんな姉弟2人のやりとりを黙って見ていたロックだが、不意に玄関扉の方を向き、その後また祐也の背中によじ登ってきた。 「いてててて、ロックまたかよ」 そんなロックをいつもの様に祐也の背中から降ろそうとした真美だが、今回に限ってロックは強く爪をたてしがみつく。 「どうしたのかしら?この子今日は降りない」 「え〜?どうすんだよこいつ」 「仕方ないじゃない、そのまま行って来なさいよ」 「おいおい、冗談じゃないぜ。このままじゃ店に入れないじゃないか」 「あら、それは大丈夫じゃない?今日のこの時間なら駿君がいるんでしょ?駿君に頼んで降ろしてもらうか、代わりに買ってもらえば良いのよ」 「え〜駿にそんな事言うのか?」 「だってそれしか方法がないじゃない。ちゃんと携帯持ってるんでしょ?」 「持ってるけどさ」 「ロックがどうしても降りなかったら店に電話して駿君に事情を説明しなさい」 「だったら姉ちゃんが行けば良いだろ」 「あらだめよ、この後明日のお弁当の下拵えしなくちゃいけないんだから。それとも明日のお弁当、あんたのだけじゃ無く、駿君の分も無いけどそれでも良いの?」 「ぐっ」 弁当の件を出されると祐也の立場は弱い。 渋々祐也はロックを背中につけたままコンビニに向かった。 ポケットに手をつっこんで歩きながら祐也は背中のロック相手に悪態をつく。 「お前なぁ、店に着いたら背中から降りろよ。どんな店も動物の出入りは禁止なんだからな」 だがロックはそんな祐也の言葉など聞こえていない様子で自分の前足をペロペロ舐めていた。 だが祐也とロックがコンビニの駐車場に足を踏み入れた時、突然ロックが祐也の背中から地面に降り立った。 それだけではなくロックは店の入り口めがけて走り出した。 そんなロックに驚いた祐也は慌てて追いかける。 「こらロック待て!」 そのままロックを追いかけた勢いで店内に足を踏み入れた祐也が最初に見たのは、薄汚れた作業ズボンとやはり薄汚れたスニーカーを履いた見知らぬ男の足下でその男に向かってしっぽを膨らませながらシャー!と威嚇をしているロックの姿だった。 その様に慌てた祐也は男に謝罪しようと視線をあげる。 すると次に目に入ったのはカウンターの中で青ざめながら数枚の紙幣を握りしめている駿の姿であった。 最初は男に渡す為のお釣りかと思った祐也だがすぐに違和感に気づいた。 駿が握りしめているのはお釣りには絶対使わない一万円札なのである。 祐也はそのまま男の方に視線を移す。 男は駿に向かって左手を差し出していた。そして右手には出刃包丁が・・・・・・。 『強盗』 その2文字が祐也の頭に浮かんだ途端ロックが何故かカウンターに飛び乗った。そしてカウンターから男に向かってしっぽを膨らませながら威嚇する。 「なんだこの猫!」 強盗が苛立った声をあげた途端祐也の身体が動いた。 あっという間に強盗のもとまで行くと、右足でしっかりと床を踏みしめ、左足で強盗の腹を蹴り飛ばした。 いわゆる回し蹴りである。 祐也は空手等の格闘技をやっていた訳ではないが、ずっとサッカーをしていたためとっっさに足での攻撃が頭に浮かんだのである。 「ぐはぁっ!」 横からの攻撃など全く想像していなかった強盗はそのまま後ろに吹っ飛びガムやアメ等の陳列棚に激突した。 「くそ・・・・・・」 商品に埋もれながら何とか立ち上がろうとした強盗だが祐也と駿の行動は素早かった。 祐也が背中に乗って、強盗の動きを封じながらポケットに入れていた携帯で警察を呼んでいる間に駿は商品のビニールテープを持ってきて後ろ手に強盗の手と足を縛った。 そうして床に落ちていた包丁もやはり商品のタオルでくるんで回収した。 そうしてようやく落ち着いた頃には2人共疲労困憊していた。 「大丈夫か?駿」 「うん、やばかったよ。あのままだったら売上金のほとんどを持って行かれるところだった。祐也が来てくれて助かった、それにロックもそいつの気をそらしてくれたから」 駿は祐也の下でなおももがいている強盗に視線を向ける。 「そういえばロックが威嚇してこいつの気をそらせてくれたからうまく蹴りが入ったんだよな。こいつはやっぱり幸せの黒猫なんだな」 そして噂のロックは再び祐也の背中に登って来た。 だが今回だけは祐也は何も言わずにロックの好きにさせるのであった。 そんな事を話している内にようやく警察が到着して、強盗は連行されて行った。 ところがその後店内で祐也と駿2人が警察から事情聴取を受けている最中、連絡を受けたコンビニの店長が入り口から入って来た時祐也の背中から降りていたロックはそのままスルリと店外へと出て行った。 そしてロックは2度と木下家には帰って来なかった。 ロックがいなくなり、祐也はもちろん真美は大いに悲しんだ。 だがその後ロックがいなくなり悲しんでいる真美にラッキーが訪れた。 イケメンエリート斉藤と真美が恋人同士になったのだ。 何でもロックがいなくなったことで落ち込んでいた真美を斉藤が慰めている内にそういう関係になったそうだ。 そしてロックのラッキーパワーは祐也にも効いた。 祐也と駿の活躍がありとあらゆるメディアで報道されると、駿の父を高待遇で雇いたいという企業が現れたのだ。 その事で駿はコンビニのバイトの回数を減らす事にし、サッカー部に復帰する事ができたのだ。 今祐也は駿と一緒にピッチを駆け巡りながらロックが運んでくれた幸せを噛みしめていた。 (幸せの黒い猫、完) |
